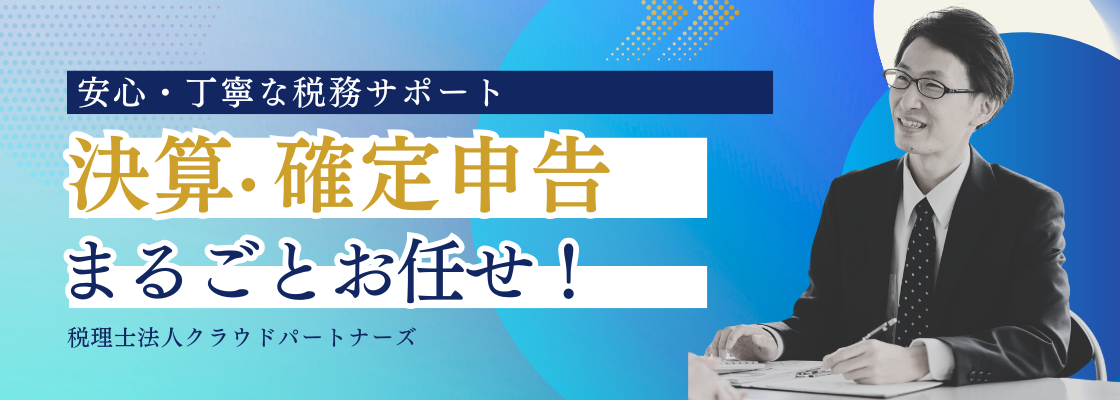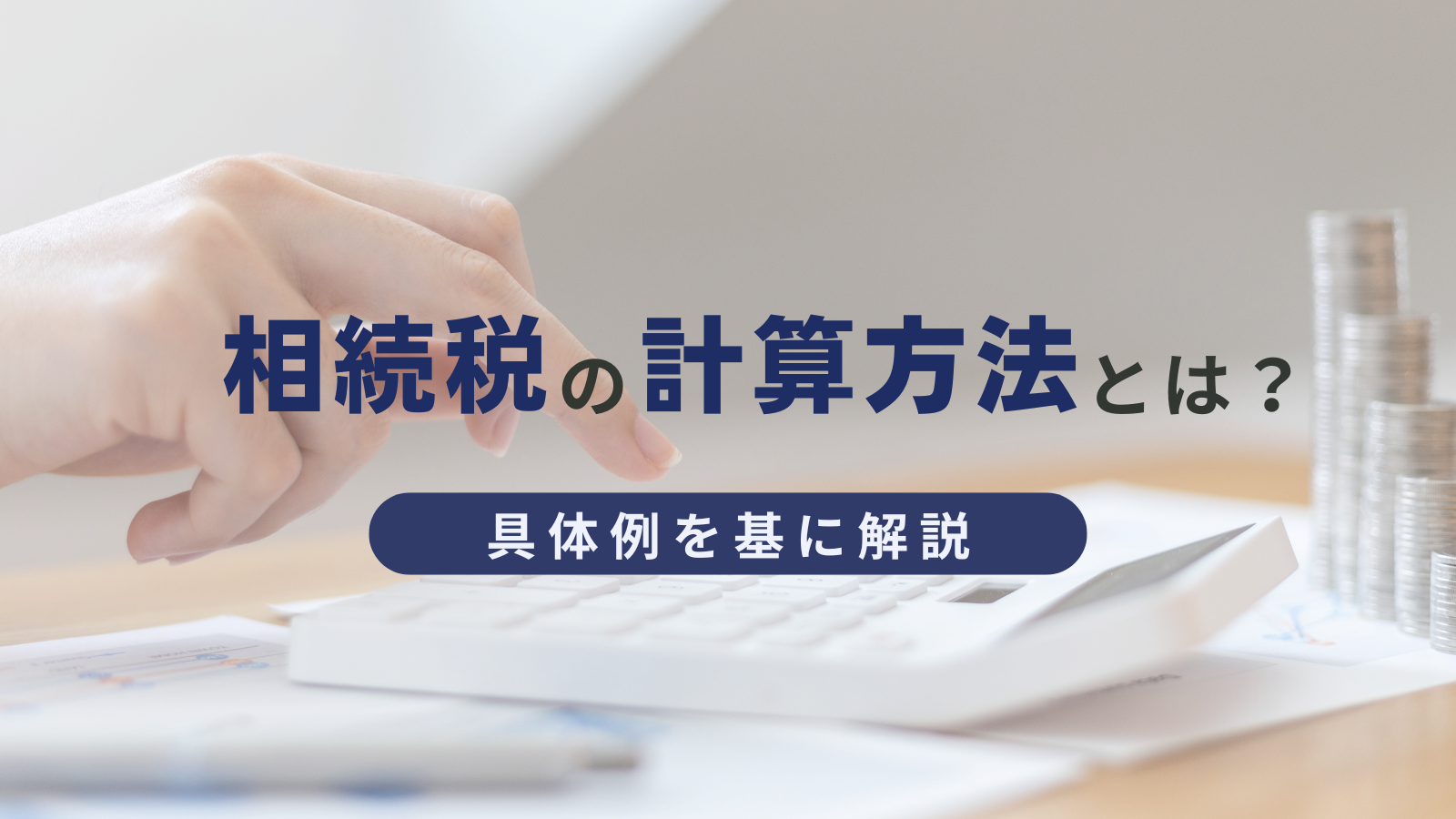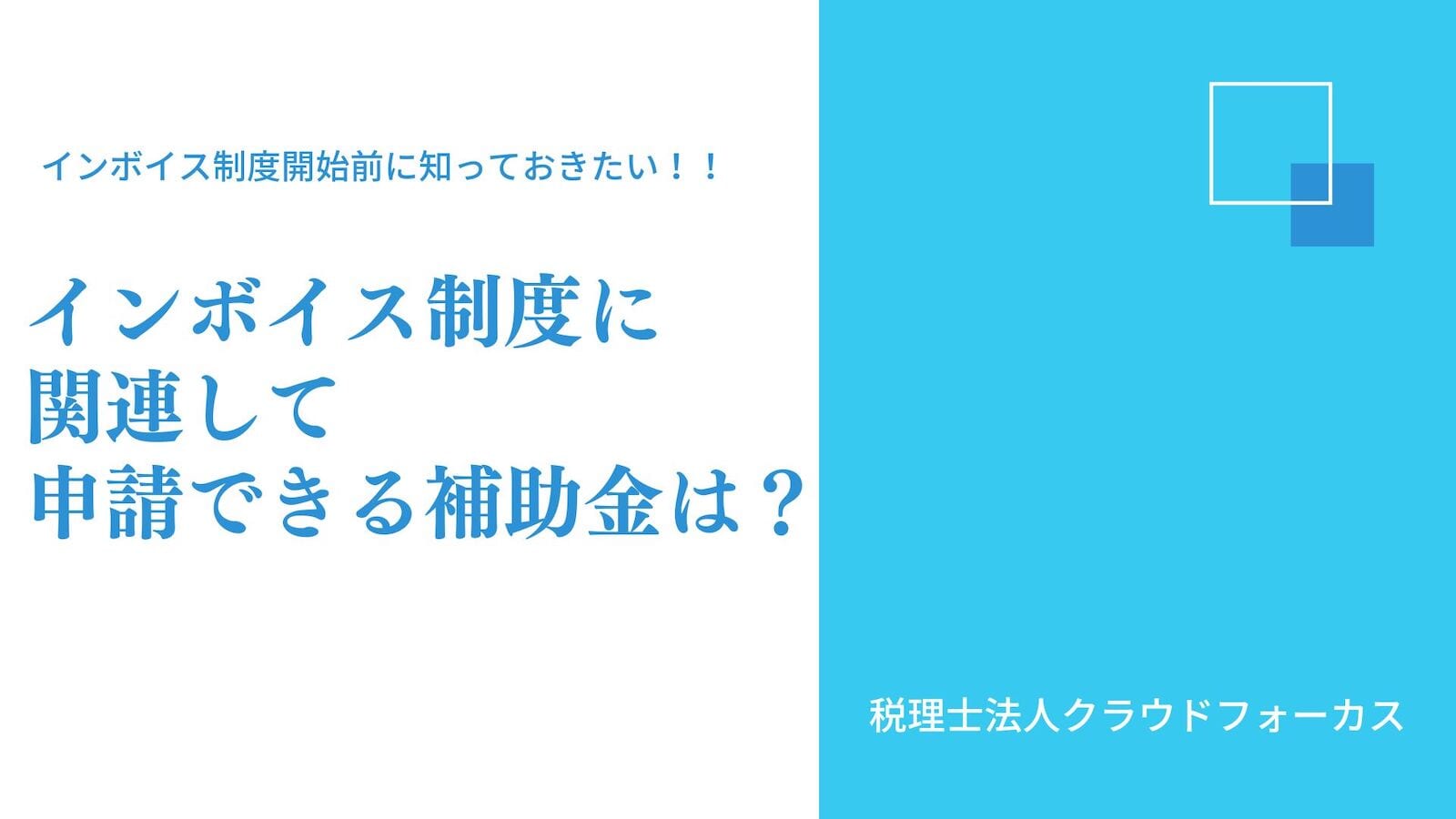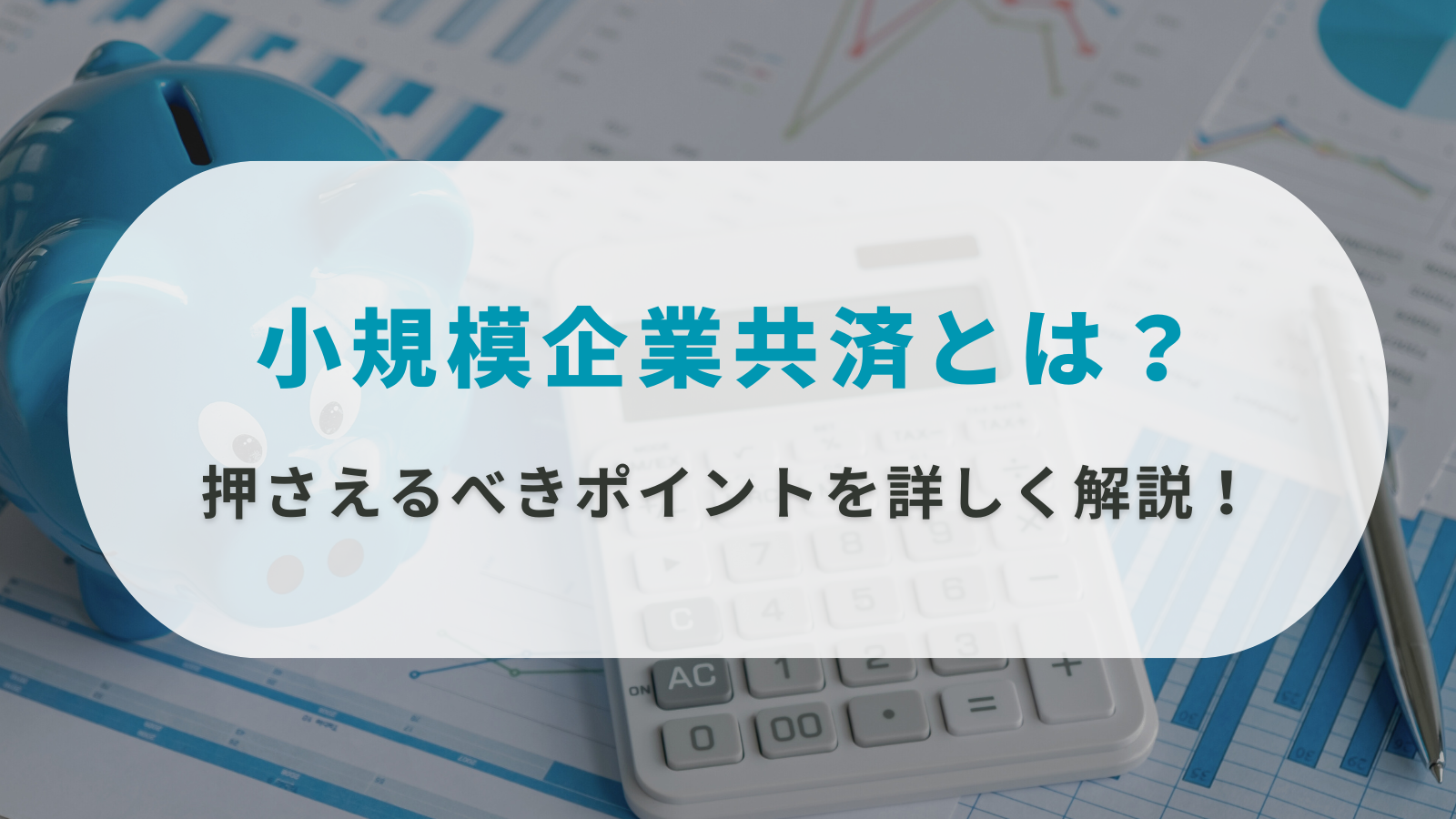
小規模企業共済とは?~押さえるべきポイントを詳しく解説!~
目次
はじめに
皆さま、小規模企業共済をご存じでしょうか?
小規模企業共済は、個人事業主はもちろん、小規模企業の経営者や役員の方でも、自らの退職金を計画的に積み立てられる制度です。
掛金は年間84万円まで全額が所得控除の対象となるため、個人の節税対策としても有効です。さらに、掛金積立額の範囲内で事業資金の貸付を受けられる「貸付制度」も用意されています。
本記事では、将来に備えながら節税も実現できる「小規模企業共済」について、詳しくご紹介します!
加入要件
小規模企業共済は、以下のいずれかに該当する場合に加入する事ができます。
※パート、アルバイトなどの非正規労働者や家族従業員、共同経営者(2人まで)の方は常時使用する従業員に含まれません。
※加入後に人数を超えた場合でも共済契約の継続は可能です。
参考:加入資格|小規模企業共済
掛金について
小規模企業共済の掛金は、月額1,000円から7万円までの範囲で500円ごとに自由に設定できます。
「今は無理なく1,000円だけ」「余裕が出てきたから増額しよう」というように、途中で掛金を増やしたり減らしたりすることも可能です。
また、掛金総額の上限が決まっていないため、現役を引退するまで、長期間じっくり積み立てることが可能です。
このようにライフプランに合わせて無理なく続けられるので、将来のことを考えながらしっかり老後資金を準備できます。
共済金等について
①共済金等の種類
小規模企業共済の共済金等の種類は、「共済金A」「共済金B」「準共済金」「解約手当金」の4つがございます。
共済金等の請求事由によって、受け取る事ができる共済金等の種類や金額が変わります。
共済金等の請求事由については、個人事業主・法人役員・共同経営者ごとに異なりますので、詳しくは以下をご確認ください。
| 共済金等の種類 | 個人事業主 | 法人の役員 | 共同経営者 |
|---|---|---|---|
| 共済金A | ・個人事業を廃業した場合 ・共済契約者の方が亡くなられた場合 | ・法人が解散した場合 | ・個人事業主の廃業に伴い、共同経営者を退任した場合 ・病気やけがのため共同経営者を退任した場合 ・共済契約者の方が亡くなられた場合 |
| 共済金B | ・老齢給付(※1) | ・病気やけが、または65歳以上で役員を退任した場合 ・共済契約者が亡くなられた場合 ・老齢給付(※1) | ・老齢給付(※1) |
| 準共済金 | ・個人事業を法人成りして加入資格がなくなり、解約した場合 | ・法人の解散、病気、けが以外の理由、または65歳未満で役員を退任した場合 | ・個人事業を法人成りして加入資格がなくなり、解約した場合 |
| 解約手当金 | ・任意解約 ・機構解約(※2) ・法人成りして加入資格がなくならなかったが、解約した場合 | ・任意解約 ・機構解約(※2) | ・任意解約 ・機構解約(※2) ・共同経営者の任意退任による解約 ・個人事業を法人成りして、加入資格がなくならなかったが解約した場合 |
- ※1…65歳以上で180か月以上掛金を納付された方
- ※2…掛金を12か月以上滞納した場合
②共済金等の受取方法
小規模企業共済の共済金等の受取方法は、「一括受取り」「分割受取り」「一括受取りと分割受取りの併用」の3つがございます。
ただし、「分割受取り」や「一括受取りと分割受取りの併用」を選択する場合には、一定の要件を満たす必要がございますので、詳しくは以下リンク先にてご確認ください。
メリット
①掛金が節税対策になる!
小規模企業共済の掛金は、「小規模企業共済等掛金控除」として、全額所得控除の対象になります。
掛金は月額7万円(年間84万円)が上限ですが、その分の課税所得を減らせるため、大きな節税効果が期待できます。
以下リンク先にて、受け取れる共済金額と年間節税額のシミュレーションが可能ですので、ぜひお試しください。
②貸付制度を利用できる!
小規模企業共済の貸付制度では、これまでに支払った掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、無担保・無保証人で事業資金などを借り入れる事ができます。
有利な条件(即日貸付け可能・一般的な融資よりも低金利など)で融資を受けれるため、急に資金が必要になった際などに大変心強い制度となります。
貸付タイプによって、借入条件・借入の限度額・利率が変わりますので、詳しくは以下をご確認ください。
また、貸付タイプや借入金額によって、借入期間が変わりますので、詳しくは以下をご確認ください。
③共済金等の受取時にも税制優遇がある!
小規模企業共済は、掛金の支払時だけでなく、共済金等の受取時にも税制上の優遇措置があります。
「一括受取り」と「分割受取り」で取り扱いは異なりますが、どちらの方法でも税負担が軽減されるため、老後の資金を安心して受け取ることができます。
・一括受取り:「退職所得」扱いとなり、退職所得控除が適用されます。
・分割受取り:公的年金と同じく「雑所得」扱いとなり、公的年金等控除が適用されます。
※65歳未満の方が任意解約する場合、65歳未満の共同経営者が任意退任する場合、または12か月以上の掛金未払いによる機構解約で解約手当金を受け取る場合は、共済金等が「一時所得」として課税されますので、ご留意ください。
注意点
①任意解約する場合
小規模企業共済は、加入から20年以内に任意解約した場合、解約手当金がそれまでに支払った掛金を下回り、掛金が元本割れするリスクがあります。
特に加入から1年未満で任意解約する場合には、解約手当金が0円となります。
このように短期間での解約はリスクが大きいため、必ず長期運用を前提にご検討ください。
②掛金を減額する場合
小規模企業共済の掛金は「掛金月額変更(増額・減額)申込書」を提出することで、1か月単位で柔軟に変更することが可能です。
ただし、掛金を減額した場合、その減額分が納付月数にカウントされなくなるため、加入から20年以上経過していても、任意解約時に掛金が元本割れとなる可能性があります。
たとえば、掛金を月額5万円から2万円へ減額した場合、2万円分は減額前と同様に納付月数としてカウントされますが、差額の3万円分は納付月数としてカウントされなくなります。
掛金の減額期間が長引くほど元本割れのリスクは高まりますが、その後に増額した場合は、納付月数のカウントが再開されます。
小規模企業共済で掛金の元本を確実に回収するには、短期解約や掛金減額を避け、事業計画とライフプランに合った無理のない掛金を設定し、長期にわたり安定して払い続けることが重要です。
おわりに
小規模企業共済は、「退職金」+「節税」+「緊急資金」の3拍子がそろった、経営者や個人事業主にとって非常に心強い制度です。
長期的に積み立てることで、将来の安心だけでなく、今すぐにでも節税メリットを享受できるのが大きな魅力です。
また、急な資金需要が発生した際にも、掛金を担保に低金利で融資を受けられるため、事業のリスクヘッジとしても活用できます。
一方で、短期解約や掛金減額には元本割れのリスクが伴うため、制度の特徴と注意点を十分に理解したうえで、無理のない金額を長期的に積み立てることをおすすめします。
最後までお読みいただきありがとうございました。
少しでもお役立ていただけましたら幸いです。
ご不明な点などがございましたら、税理士法人クラウドパートナーズまでお気軽にご相談ください!