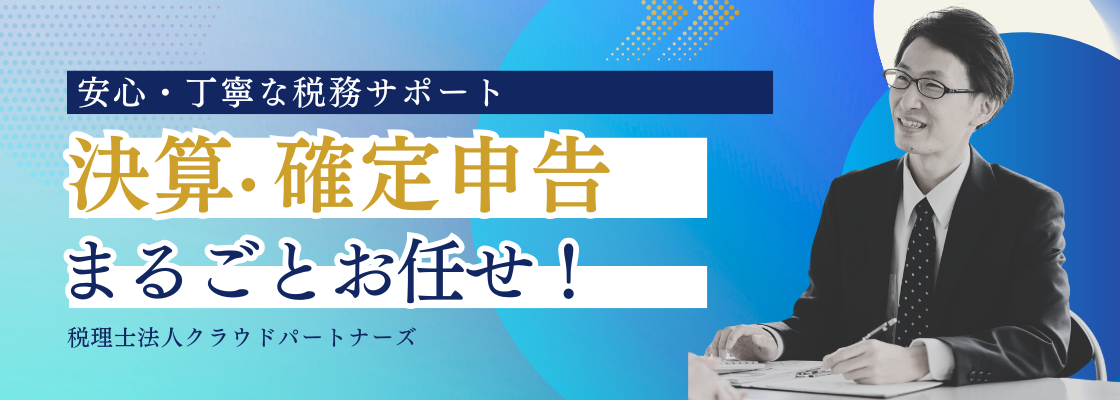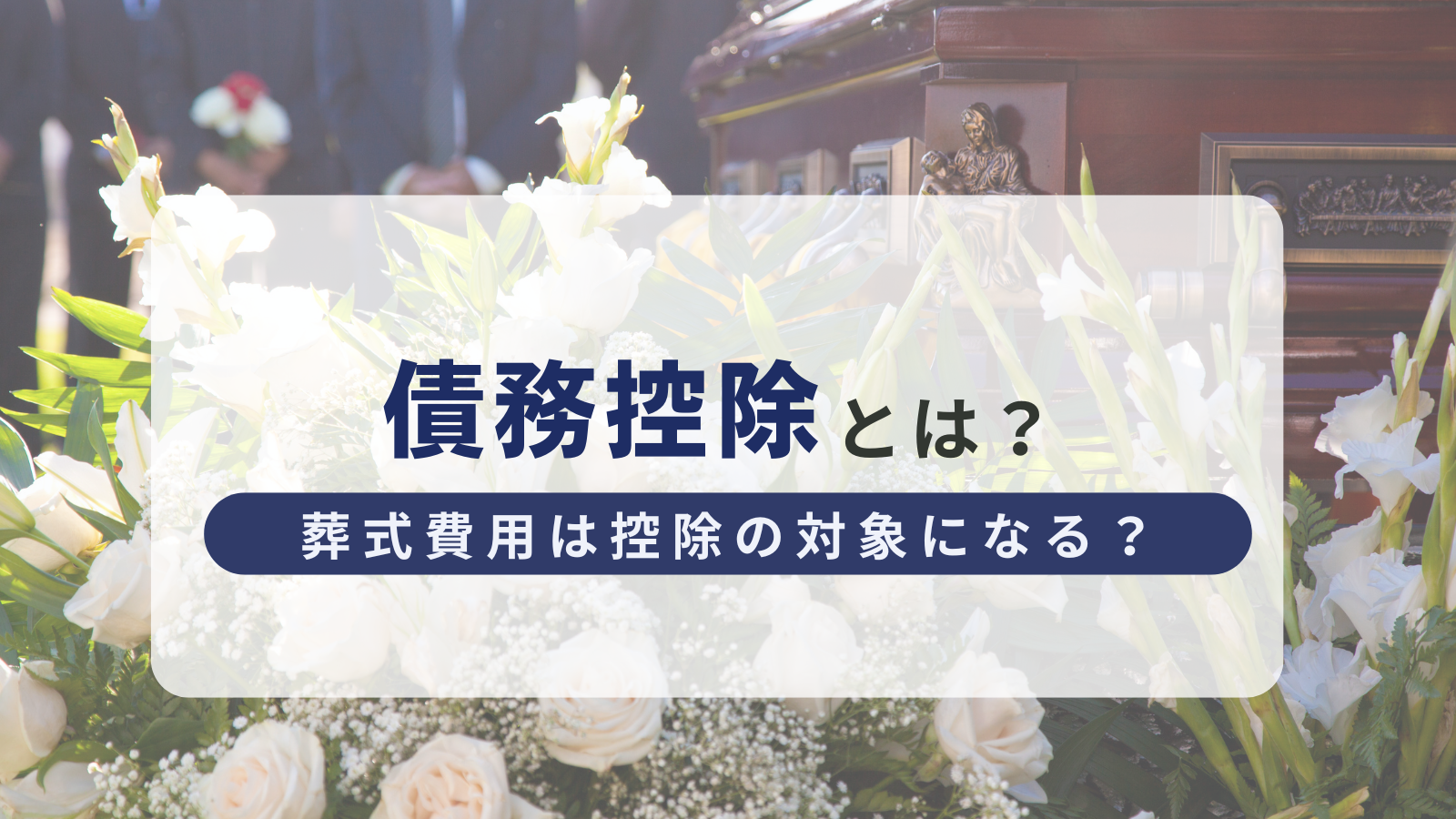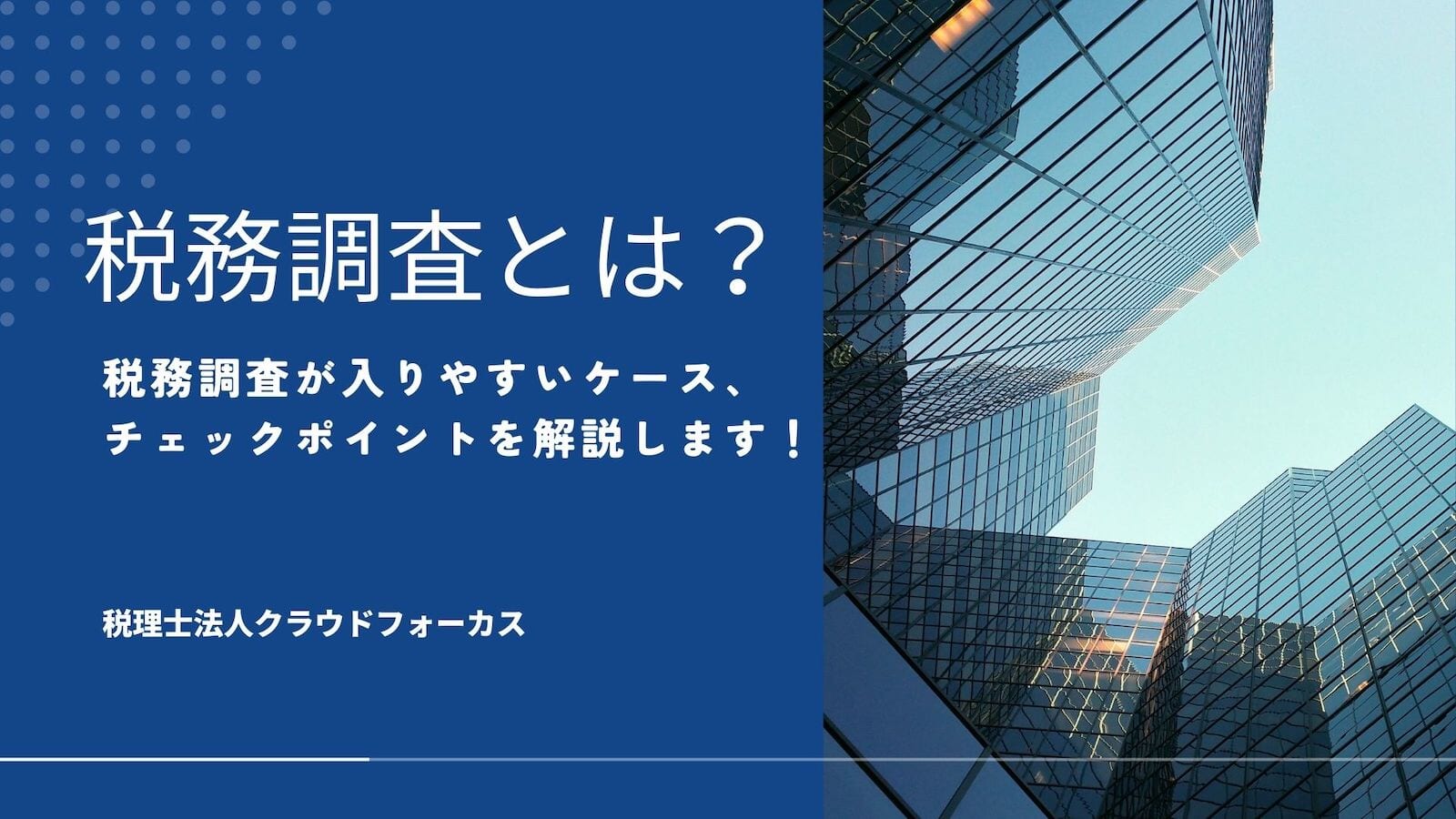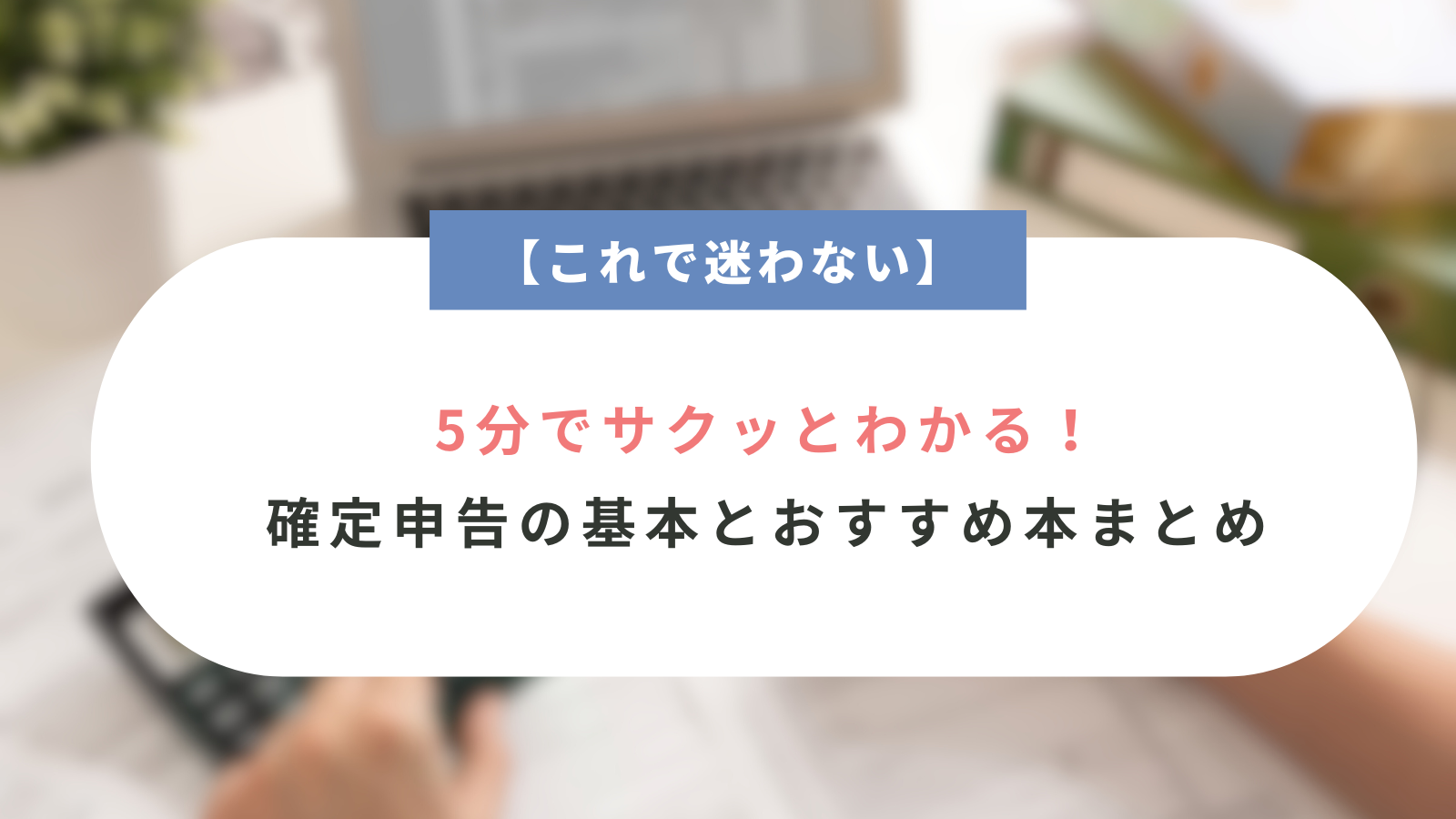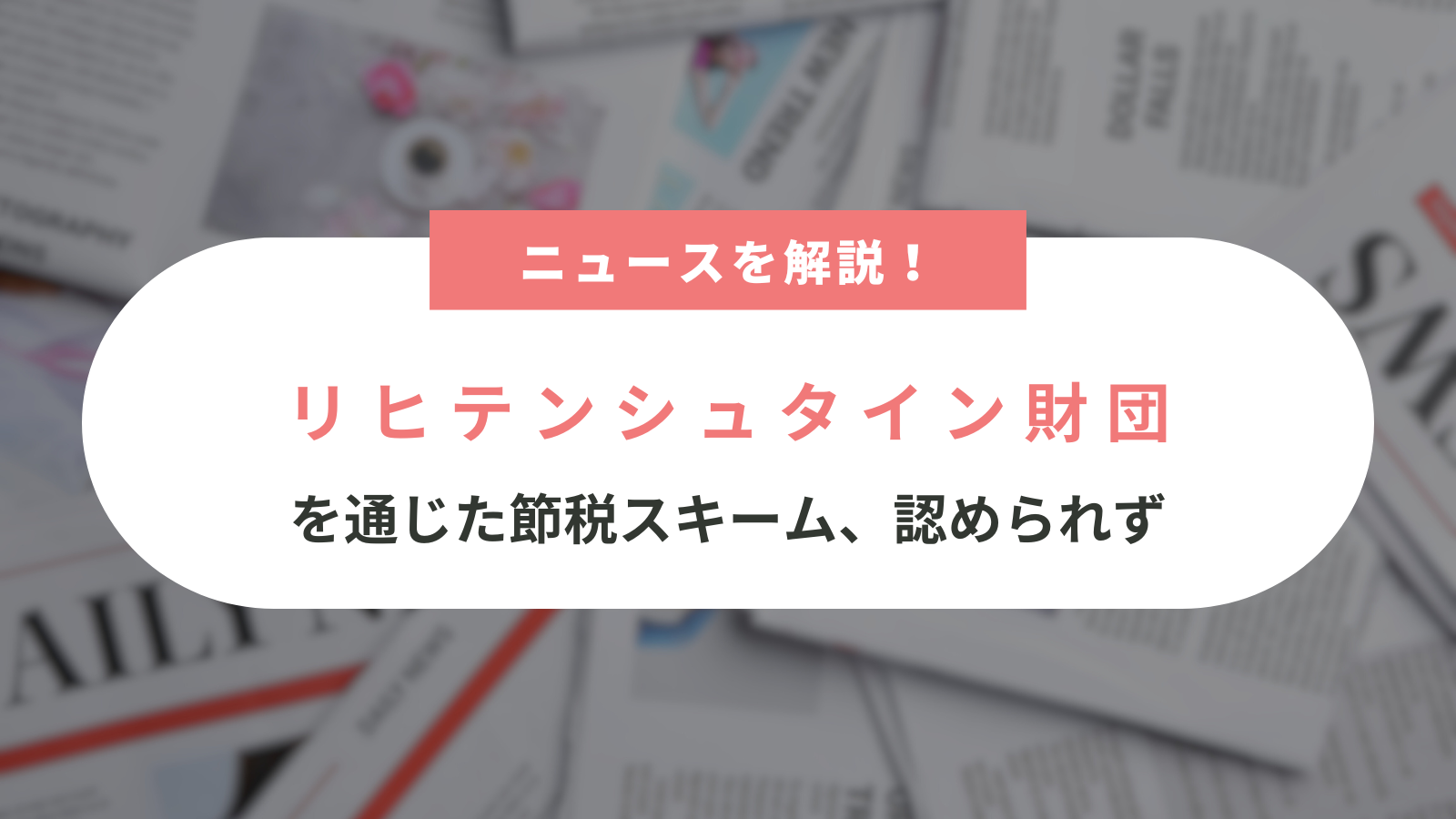
ニュースを解説|リヒテンシュタイン財団を通じた節税スキーム、認められず
目次
1 リヒテンシュタイン財団とバハマ法人を使った節税スキーム、納税者が敗訴
2025年9月、リヒテンシュタインの財団とタックスヘイブン国であるバハマを利用した節税スキームをめぐり、国税当局から追徴課税処分を受けた男性が処分の取り消しを求めた裁判の判決が東京地裁でありました。東京地裁が国税当局による課税処分を適法と認めたことから、納税者側の男性は敗訴しました。
この裁判は、海外に設立した財団や法人を通じて資産運用を行った場合、日本の税制(いわゆるタックスヘイブン対策税制)がどのように適用されるのかが争われた事案です。
2 どのような仕組みだったのか(スキームの概要)
原告である日本在住の個人男性は、次のような仕組みを構築していました。
① 男性が、リヒテンシュタインに財団を設立
② その財団がバハマ法人を設立し保有
③ バハマ法人が多額の公社債を保有し、利子収入や償還益を得る
国税当局は、男性は財団の株式を保有しているので、外国子会社合算税制(租税特別措置法第40条の4)の適用により、バハマ法人の所得は男性の雑所得であると指摘し、追徴課税を行いました。
3 争点:リヒテンシュタイン財団に「株式」はあるのか?
外国子会社合算税制(いわゆるタックスヘイブン対策税制)は、個人である日本居住者が外国法人の株式等を保有している場合に、日本側でその法人の所得をその個人の雑所得に合算する制度です。
しかし、リヒテンシュタインの「財団」には、日本の株式会社のような株式の制度が存在しません。出資者であっても株主のように議決権を持ったり、利益配分を受けたりする仕組みが明確ではないのです。
そのため、男性は、そもそも財団に株式という制度が存在せず、財団の株式を持っていないのだから、この合算税制は適用されない、と主張しました。ここが本件の最大の争点でした。
4 東京地裁の判断:「形式より実質」を重視
東京地裁は、男性は株式という形式を持たなくても、経済的・経営的に株主と同等の権利と地位を保有していると認定した上で、タックスヘイブン対策税制の適用要件を満たすとして、課税処分を適法と判断しました。
男性は控訴したようですが、法の穴をついた租税回避スキームのように見えてしまうので、控訴審でも苦しい戦いになるのではないかと感じています。