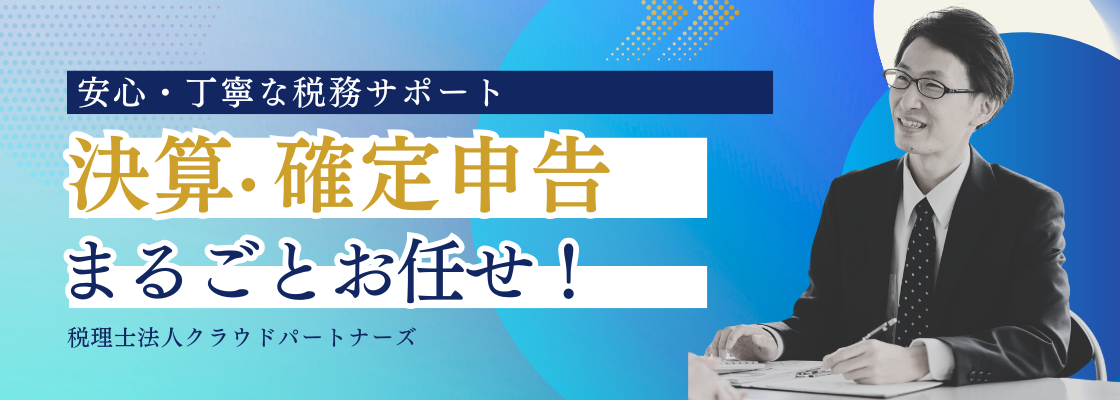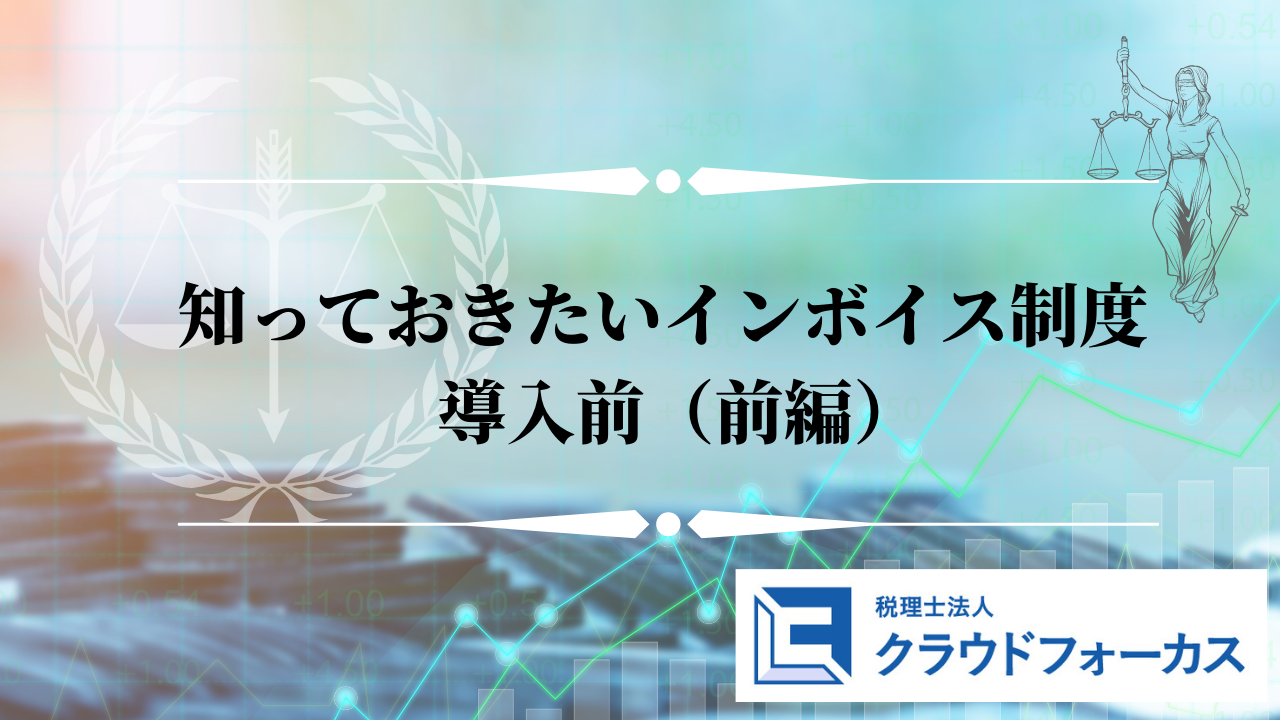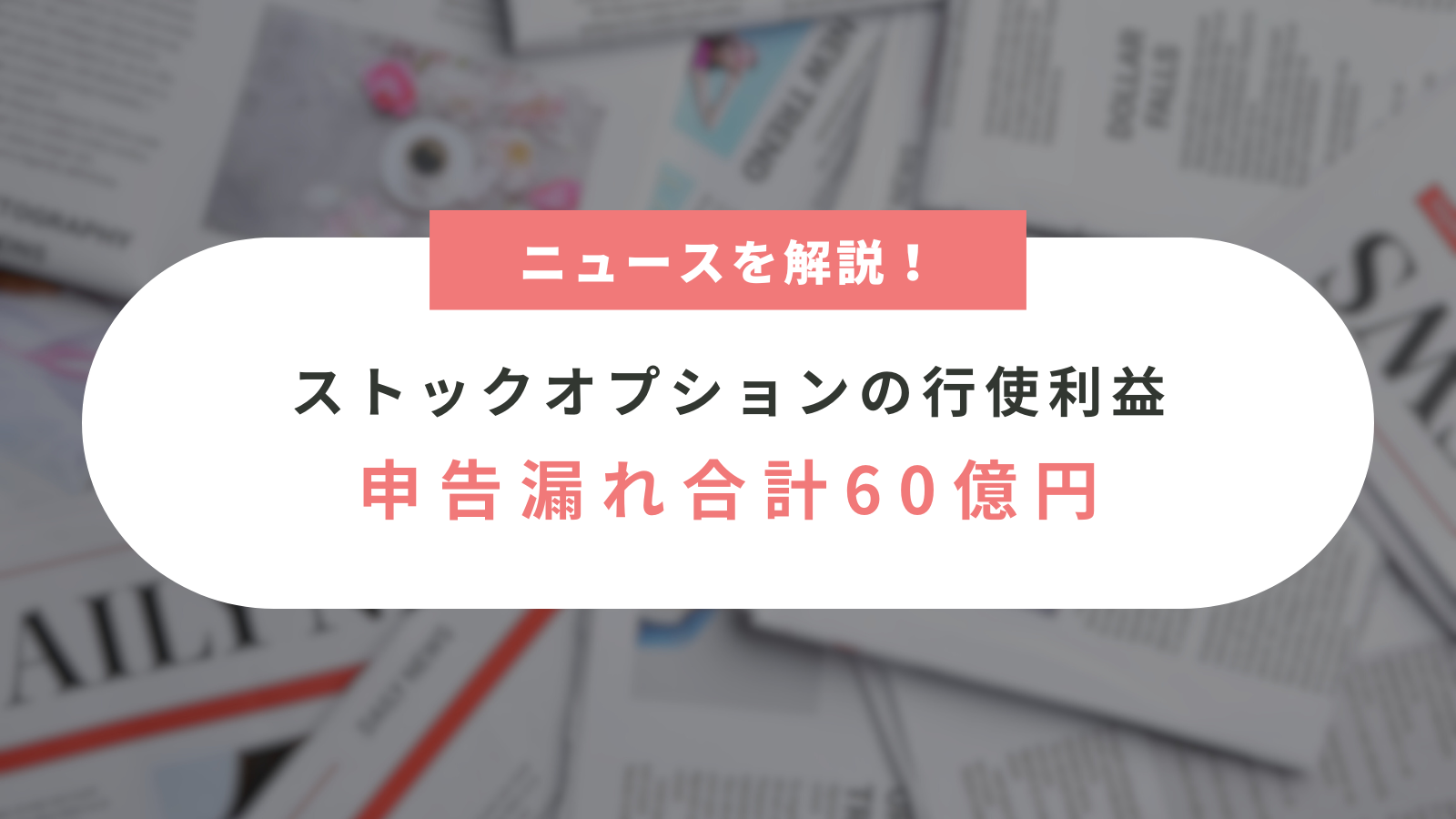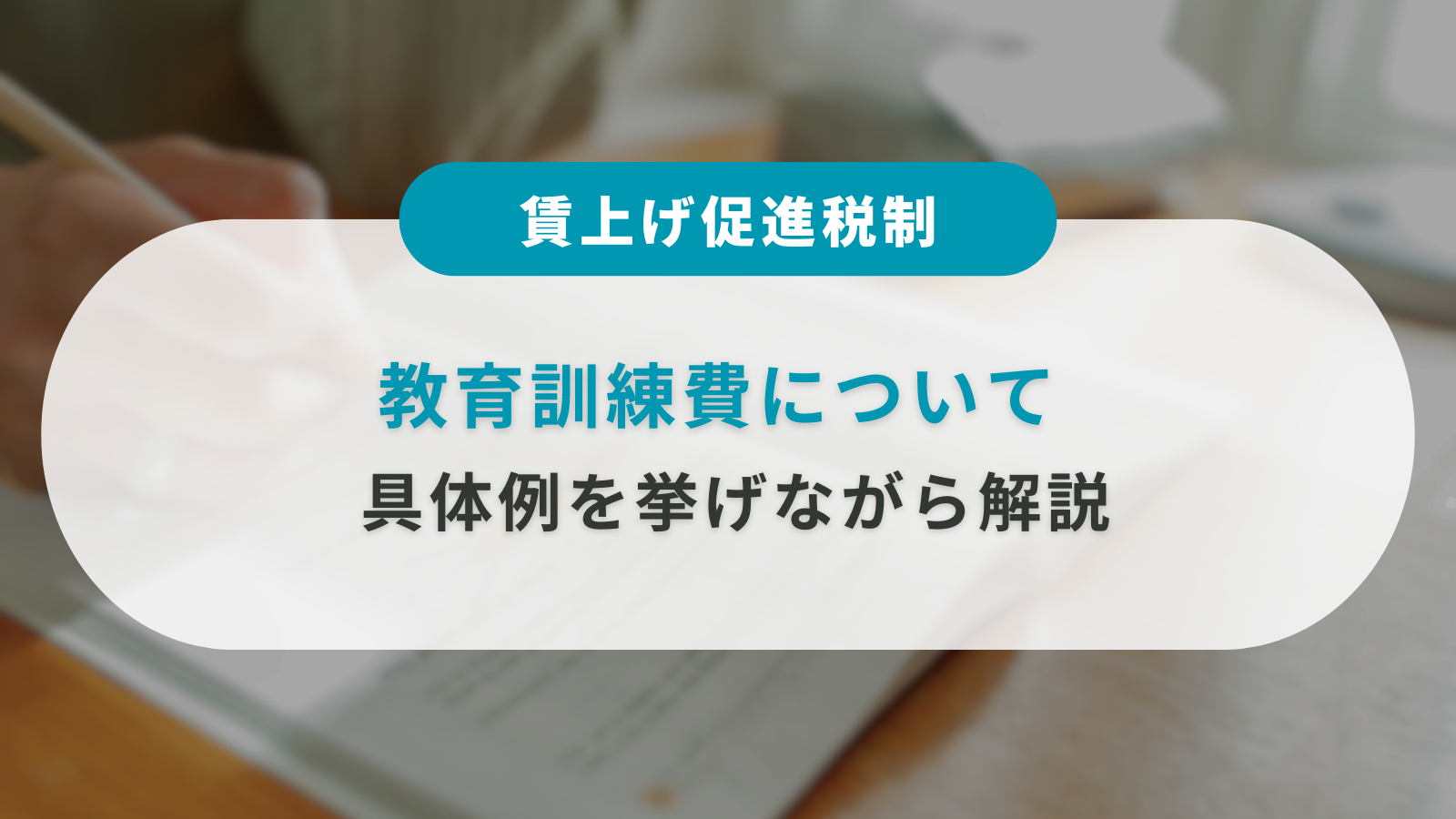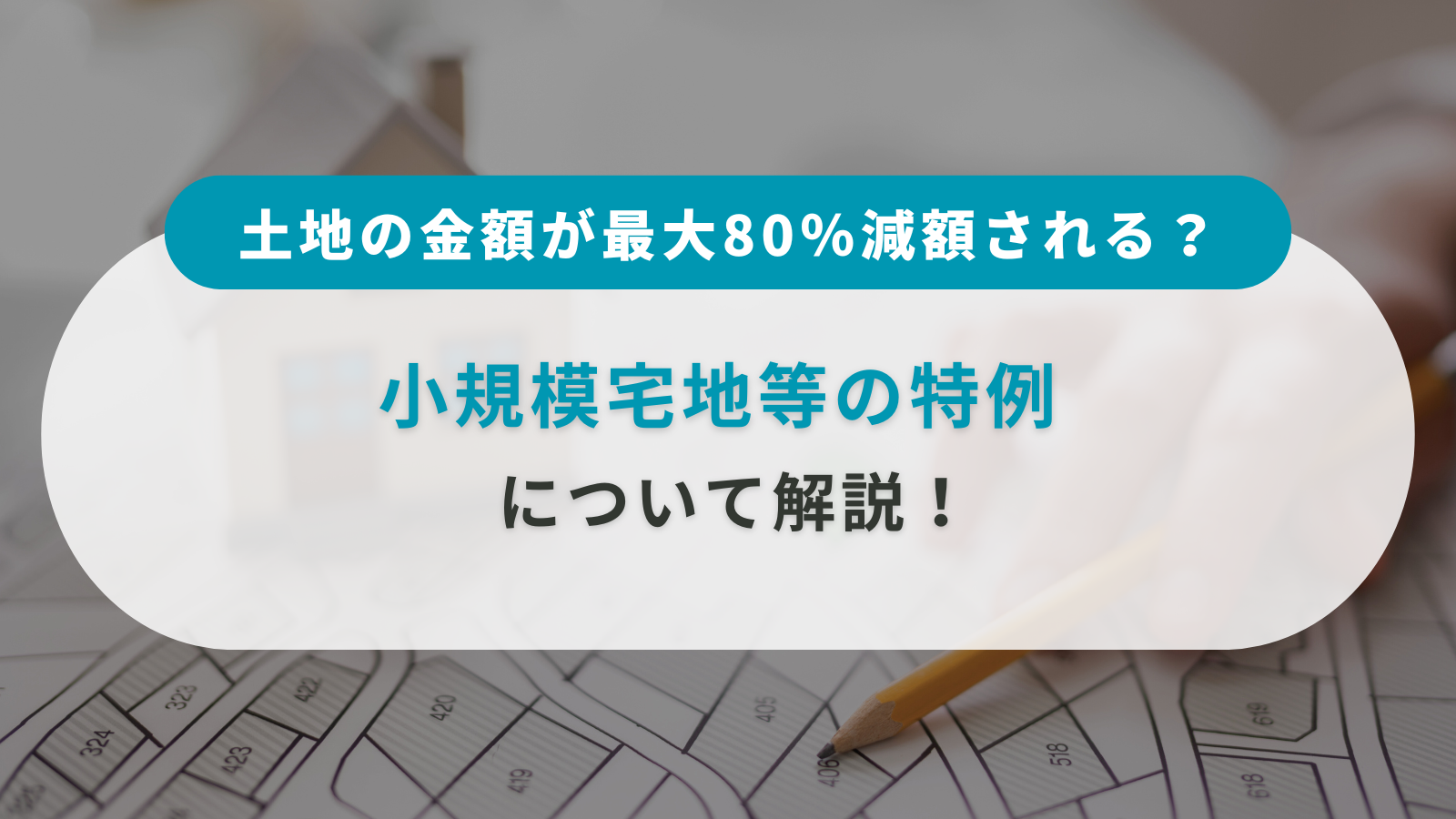
土地の金額が最大80%減額される?小規模宅地等の特例について解説!
目次
はじめに
被相続人から取得した土地で、建物や構築物の敷地として利用されているものについては、一定の要件を満たす場合に限り、その評価額が減額されます。この規定を、小規模宅地等の特例と言います。
減額される割合は最大80%と非常に大きな割合となっており、この規定を適用するか否かは相続税の計算に大きな影響を与えます。したがってご自身の相続対策を検討するうえでも、制度の内容について知っておくことは非常に重要です。
本記事では小規模宅地等の特例の内容について概要を解説させていただきます。制度の内容やどういった場合に適用ができる可能性があるのか、本記事を通してご理解いただけると幸いでございます!
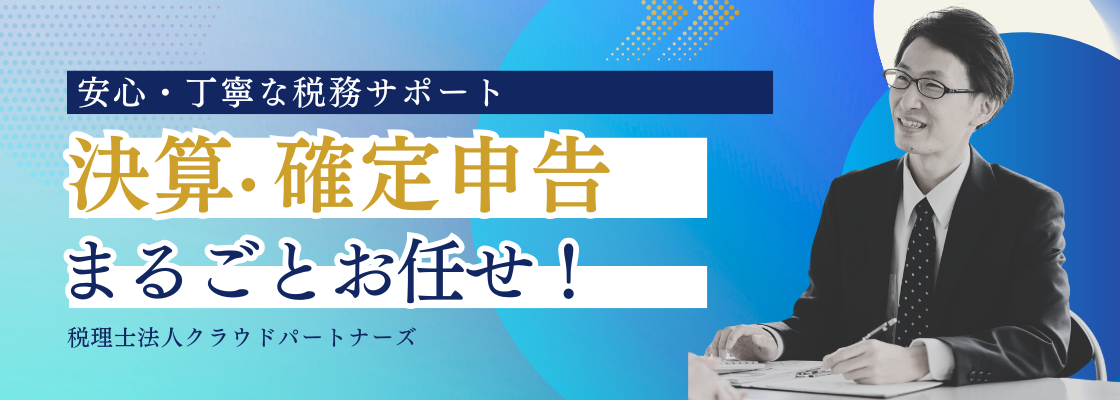
制度の趣旨
小規模宅地等の特例は、相続人の生活基盤の維持に必要と思われる財産について、相続税の負担を目的とするために設けられています。
なお制度名からも分かる通り、相続税法とは別の租税特別措置法という法律で定められた特例的な取り扱いに位置付けられます。
対象となる財産
まず小規模宅地等の特例の対象となる財産は、被相続人から取得をした宅地等※で、建物や構築物の敷地として利用されているものが該当します。構築物とは、貸駐車場のアスファルトや立体駐車場の設備などをイメージ頂ければと思います。
したがって土地の上に立っている家屋や設備は本制度の適用対象の財産にはなりえません。また建物や構築物の敷地である必要がありますので、空き地やロープなどで区切っただけなどの青空駐車場の場合は対象となりません。
※宅地等とは、土地および借地権や地上権等の土地の上に存する権利を指します。所有権がない借地権に対しても適用できるという意図で、敢えて”等”を付けて表記しています。
適用要件

次に宅地等のうち、どのような場合に小規模宅地等の特例の適用ができるかを見ていきます。細かい要件は非常に複雑になりますので、まずは概要を理解していただくことを優先し、詳細な内容については省略しております。
1.相続開始の直前において被相続人等※の事業または居住の用に供している事
1つ目の要件は、その宅地等を相続開始時に誰がどのように使っていたか、という要件です。具体的には、被相続人等がその相続の開始の直前においてその宅地等を①事業のために使用していた場合、または②その宅地等に居住していた場合です。
分かりやすい例では、被相続人の自宅が建っている宅地や、被相続人の営む事業の店舗や被相続人が所有する賃貸アパートが立っている宅地等が該当します。
まずは被相続人の死亡時に、被相続人の事業や居住のために使用している宅地等については適用がある可能性があるとご理解ください。その他、宅地等の区分に応じて相続税の申告期限まで売却をしていないことや事業を継続しているかという要件もあります。その宅地等をこれまでと同じように使う、という事が本制度の前提にあるとお考えいただければと思いますが、内容は非常に細かいため詳細は省略します。
※”被相続人等”は被相続人と被相続人の生計一親族を指しています。例えば被相続人の土地に生計を一にする配偶者が行う事業の店舗が立っていた場合で、配偶者がその土地を取得し、事業を継続することで小規模宅地等の特例の適用ができます。
2.被相続人の親族がその宅地等を取得する事
2つ目は取得する者に関する要件です。小規模宅地等の特例の適用は、対象となる宅地を被相続人の親族が取得している場合に限られます。この親族とは「配偶者及び6親等以内の血族、3親等以内の姻族」を言います。3親等の姻族が配偶者の甥・姪になりますので、範囲は比較的広いと考えて頂いて差し支えありません。
逆に、遺言によって血縁関係のない者に宅地等の遺贈をした場合には注意が必要です。特に内縁関係のパートナーや配偶者の連れ子は血縁関係がない者とみなされますので、要注意です。
3.その宅地の遺産分割が完了していること
大きな要件の3つ目は、相続税の申告期限(相続開始日から10ヶ月を経過する日)までにその宅地の遺産分割が完了している事です。もし相続争いがあったことにより申告期限までに遺産分割がまとまらなかった場合、小規模宅地等の特例は適用できない事に注意をしましょう。先に述べた通り、小規模宅地等の特例は宅地の評価額が最大8割減となるため、これが適用できないことによる影響は非常に大きなものになります。
ただこちらは一定の届出を行い、申告期限から3年以内に分割が完了した場合には後から適用を受けることで多く支払っている相続税の還付を受けることができます。
小規模宅地等の特例の内容
次に小規模宅地等の特例により宅地等の評価額がどのように変わるのかを見ていきます。
小規模宅地等の特例の対象になる宅地等(以下、特例対象宅地等と記載します)は、大きく4つに分類されます。それぞれの場合の影響額、限度面積は下記の通りです。
| 小規模宅地等の区分 | 減額割合 | 限度面積 |
| 特定事業用宅地等 | 80% | 400㎡ |
| 特定同族会社事業用宅地等 | 80% | 400㎡ |
| 特定居住用宅地等 | 80% | 330㎡ |
| 貸付事業用宅地等 | 50% | 200㎡ |
例えば特定事業用宅地等(面積:300㎡)の評価額が3,000万円だったとすると、小規模宅地等の特例を適用することで評価額を600万円まで減額できるということになります。
なお限度面積はその宅地等のうち適用できる限度の面積を指しています。例えば700㎡の特定居住用宅地等については、そのうち330㎡まで適用を受けることができます。
その他、異なる区分の特例対象宅地等が複数ある場合の適用ルールもあります。複雑になるので詳細は省略しますが、複数の区分の特例対象宅地等に対して無制限に適用できるわけではない、という事は覚えておいてください。
特例対象宅地等の種類
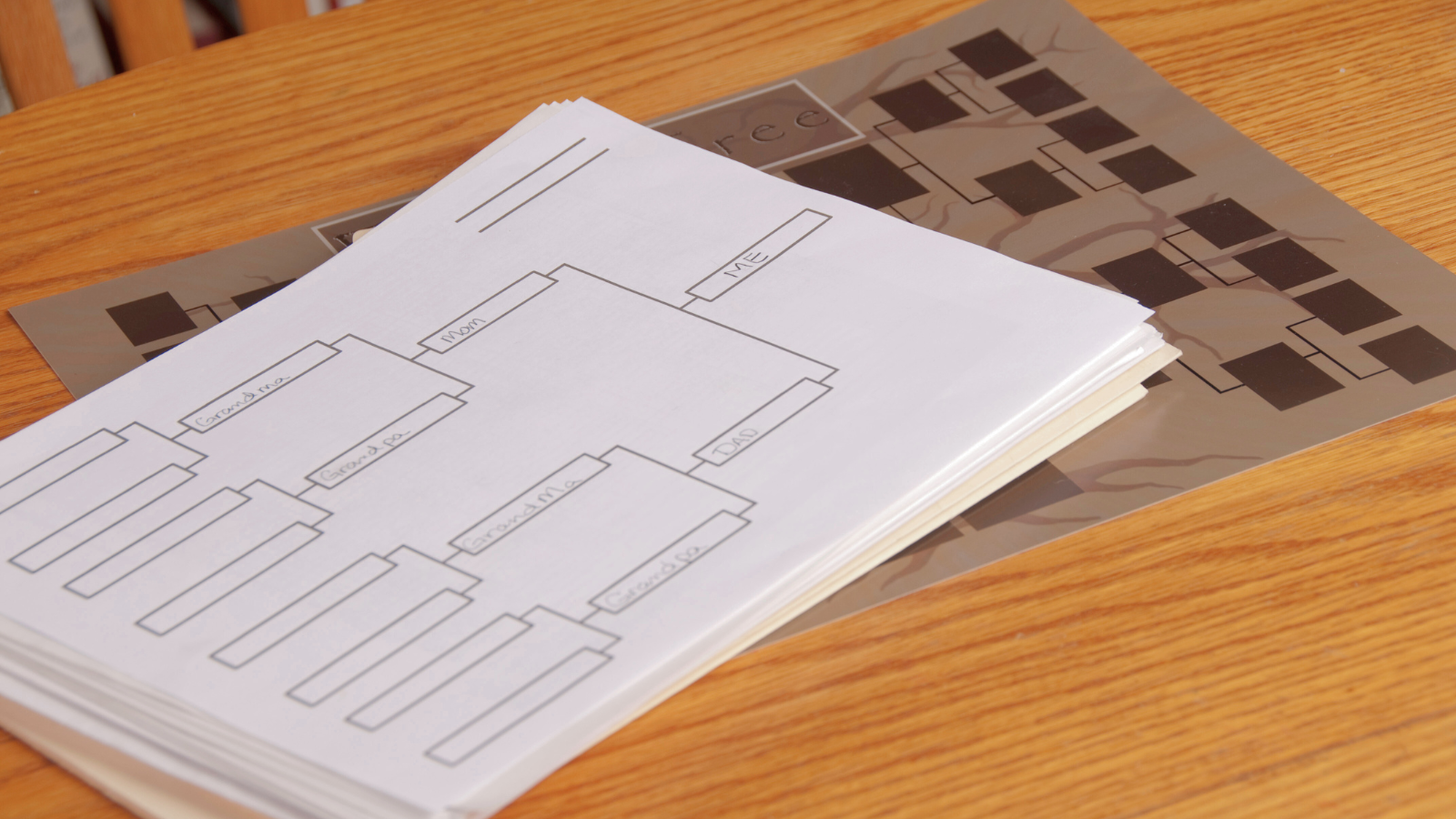
最後に上記の特例対象宅地等の区分はどのようにして決まるのかを説明します。少々複雑ではありますが、そのグループに該当するかで減額の割合・限度面積が異なってきますのでここで説明をさせていただきます。
①特定事業用宅地等
相続開始の直前において被相続人等の事業の用に供している宅地等の内、いわゆる不動産の貸付事業(その宅地等を駐車場にして貸している、アパートを建てて貸し付けている)以外の事業の用に供しているもののうち、一定の要件を満たすものを特定事業用宅地等と言います。例えば被相続人が営む事業の店舗や事務所として使用していた宅地等が該当します。
なお上記の一定の要件には、相続開始までに3年を超えて事業の継続をしている事、その宅地等を取得した親族が事業を引き継ぐこと等、細かく設定されています。
②特定同族会社事業用宅地等
相続開始の直前において被相続人の特定同族会社の事業の用(貸付事業を除く)に供されていた場合において、その宅地等を取得した親族が以下の要件を満たす場合のその宅地等が該当します。ここで特定同族会社とは、相続開始直前の被相続人および同族関係者の議決権割合が50%超である法人を言います。
- 申告期限においてその法人の役員であること
- 申告期限までその宅地等を所有していること
- 申告期限まで特定同族会社の事業のように供していること
少々難解な説明になりましたが、要するに被相続人及びその親族がオーナーである企業の事業の用に供している場合には、①の特定事業用宅地等に準ずるような取り扱いを認めるという事です。
なお特定同族会社の事業が不動産賃貸業等の場合、特定同族会社事業用宅地等ではなく④の貸付事業用宅地等に該当します。特定同族会社事業用宅地等に該当するか否かについては要件が複雑ですので、判断に迷う場合には税理士への相談をお勧めいたします。
③特定居住用宅地等
相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供していた宅地等で一定のものが該当します。被相続人の自宅の土地等を被相続人の配偶者が取得した場合、基本的には特定居住用宅地等に該当すると考えて頂いて構いません。
なお死亡時に入院をしていた、あるいは老人ホームに入っていたという場合のご自宅については、居住の用に供していたものとみなします(その間賃貸に出していた場合等一定の場合を除きます)。
その他同居している親族が取得するケース、一人暮らしで同居親族がおらず、別居している親族が取得するケースが考えられますが、この場合でも状況によっては特定居住用宅地等に該当する可能性があります。こちらは複雑な要件がございますので、気になる場合には税理士にご相談いただく事をお勧めいたします。
④貸付事業用宅地等
相続開始の直前において被相続人等の事業の用に供している宅地等の内、いわゆる不動産の貸付事業の用に供しているものの内、一定の要件を満たすものを特定事業用宅地等と言います。具体的には貸駐車場や賃貸住宅が立っている宅地が該当します。
なお上記の一定の要件には、相続開始までに3年を超えて貸付事業の継続をしている事、その宅地等を取得した親族が貸付事業を引き継ぐこと等、少々細かく設定されています。
まとめ
本記事では小規模宅地等の特例についてその概要を説明いたしました。土地の評価額への影響は非常に大きい一方で、要件が非常に複雑な制度でもございます。まずは大枠のご理解をする上でお役に建てていただければ幸いでございます!
また実際に小規模宅地等の特例が適用できるかどうか判断に迷う場合には、事前に専門家への相談をして頂くのがお勧めです。
税理士法人クラウドパートナーズでは相続対策のご相談も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ!