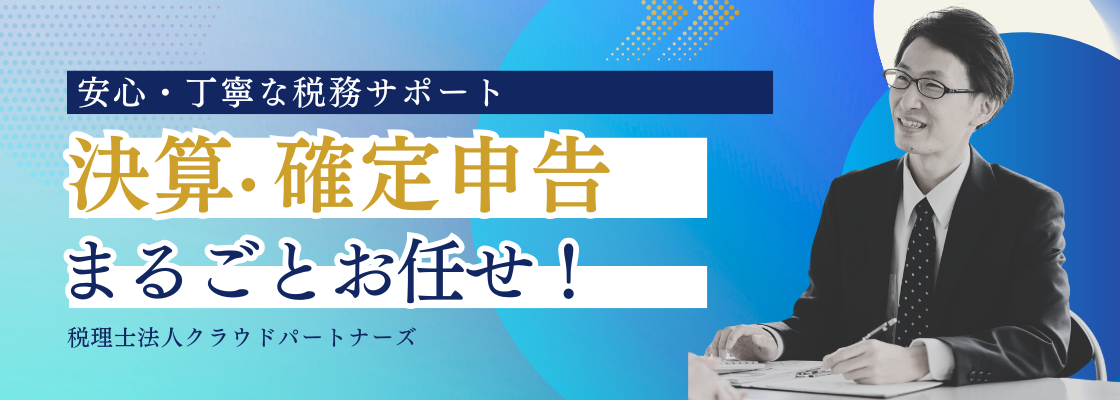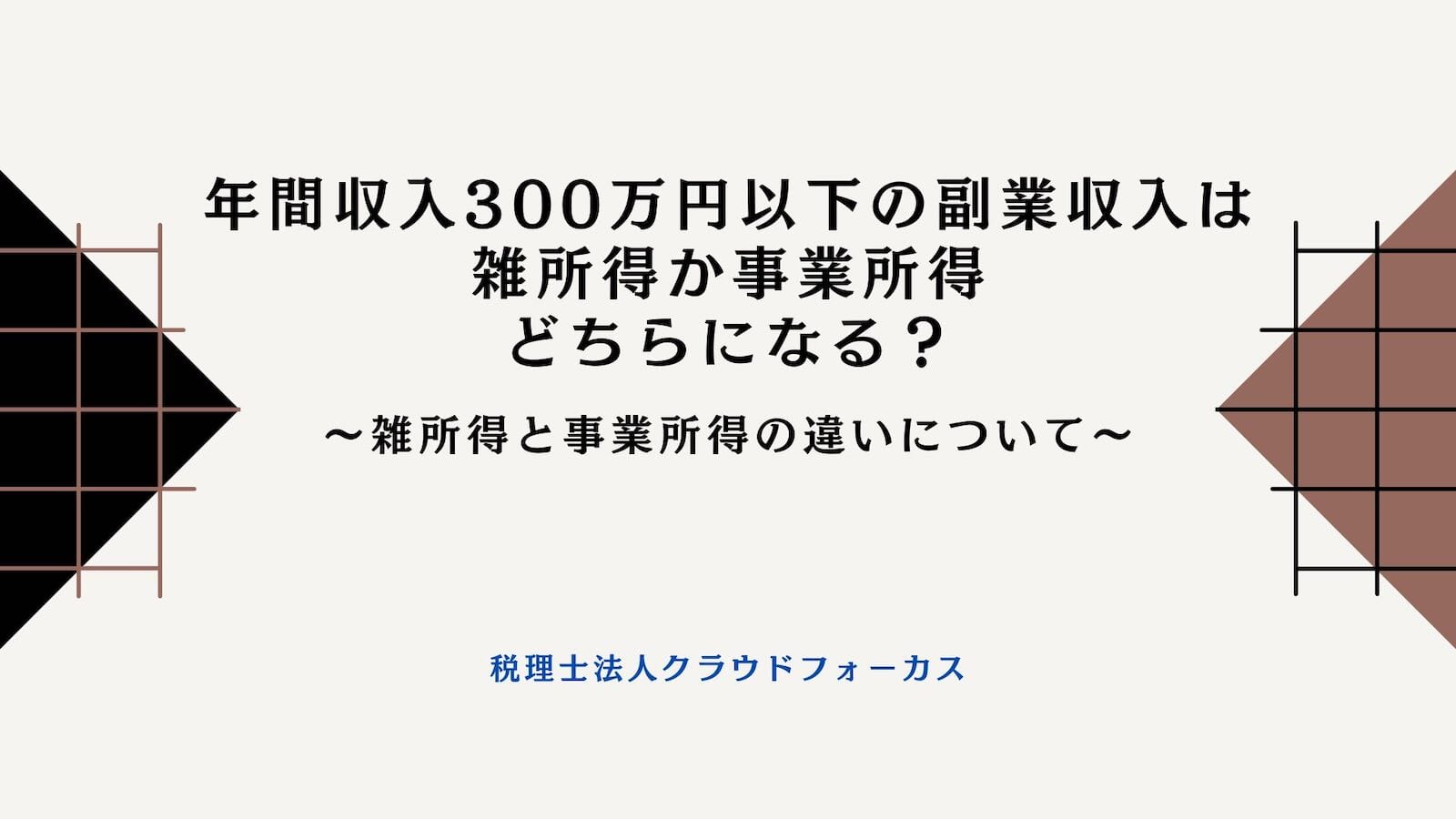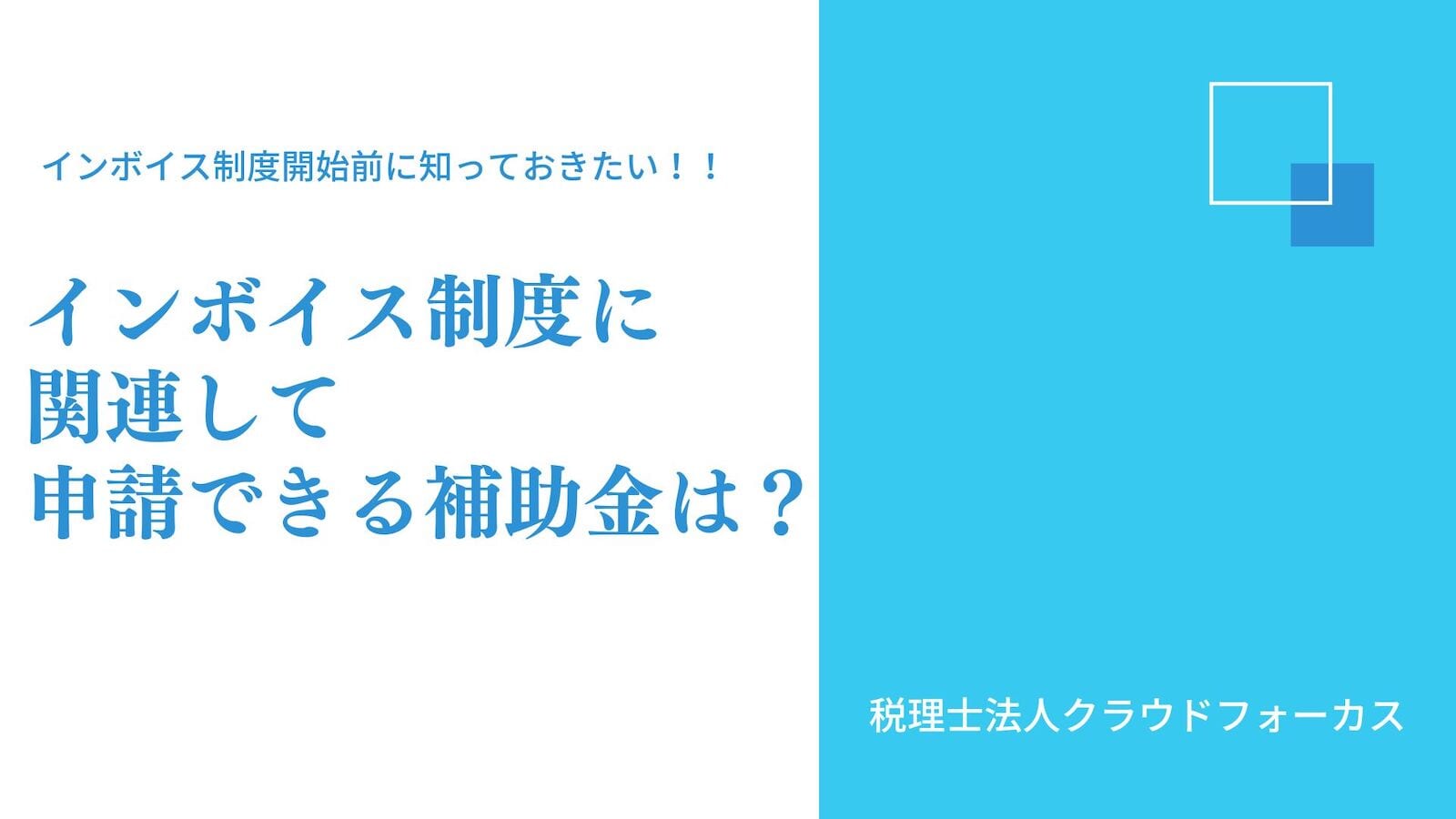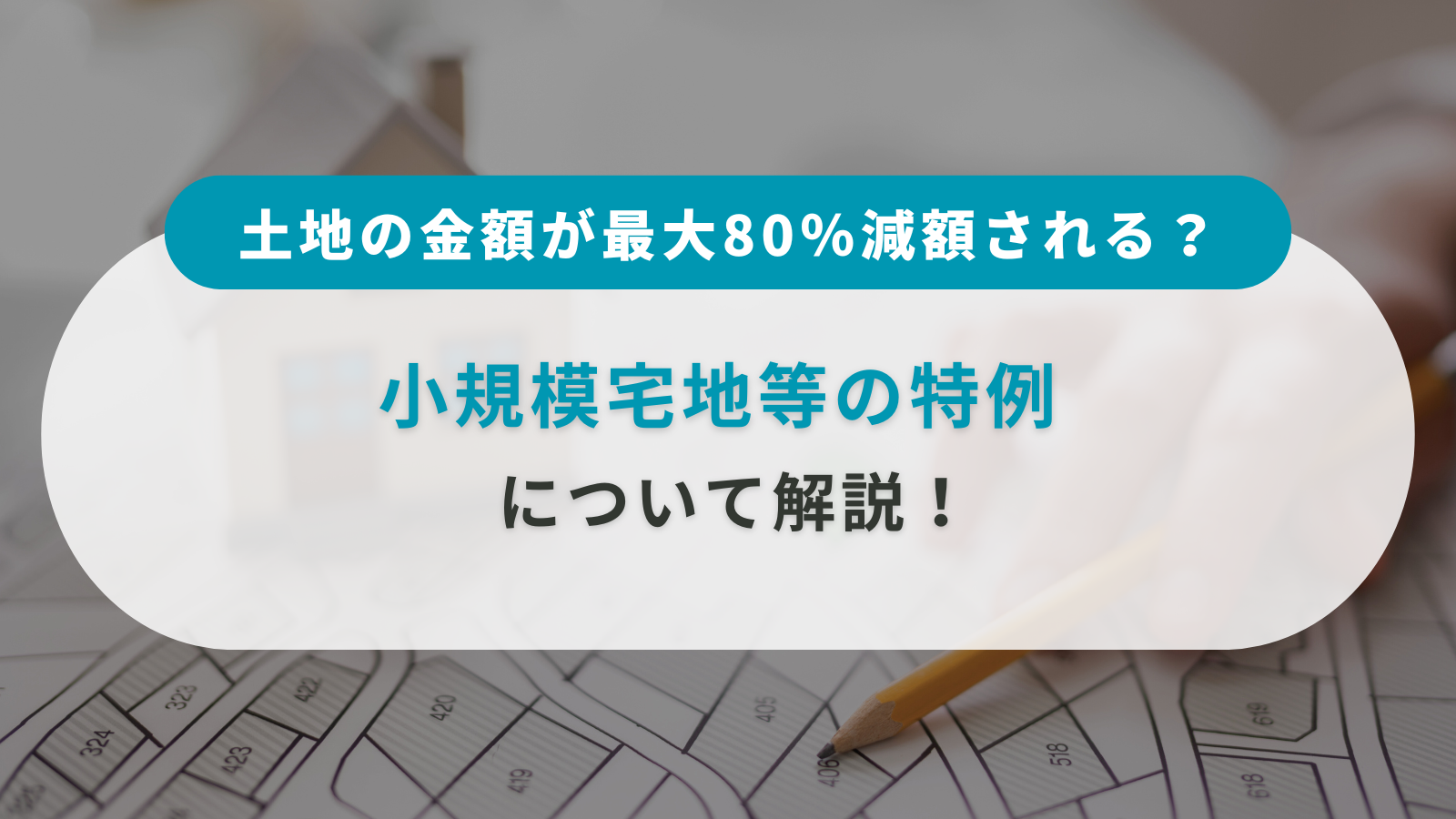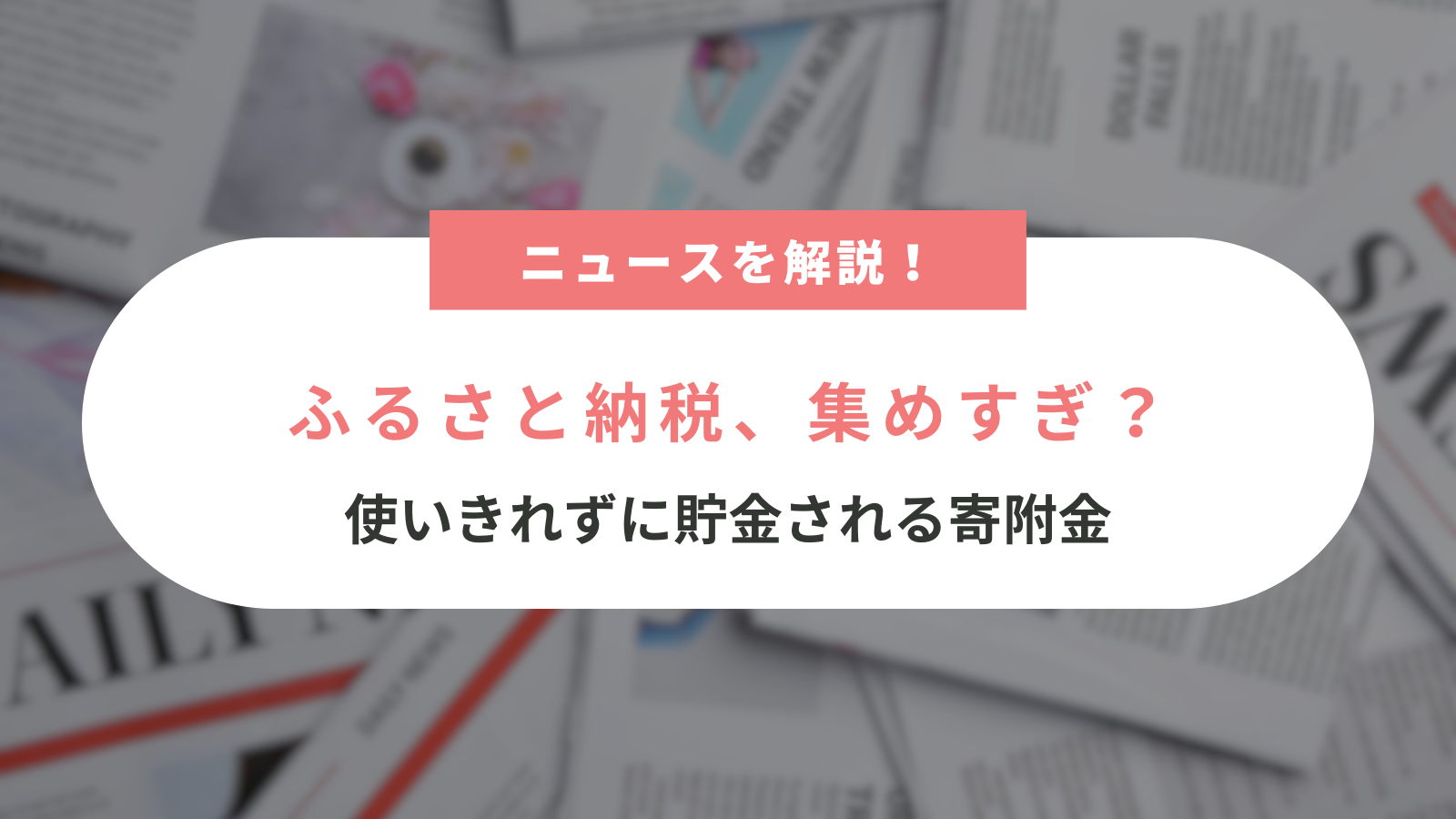
ニュースを解説|ふるさと納税、集めすぎ?使いきれずに貯金される寄附金
目次
1 ふるさと納税で集めた巨額の寄附金、使いきれず貯まっていく…
ここ数年、ふるさと納税の人気がますます高まっていますが、その一方で返礼品競争の過熱による問題も生じてきました。
特に寄附金を多く集めている上位の自治体では、ふるさと納税による寄附収入があまりにも多く、使い切れないほどの寄附金が積み上がっている状況が見られます。 総務省のデータによると、ふるさと納税で多額の寄附を集めている自治体では、「基金(自治体の貯金)」が急増しています。
2024年度までの5年間で寄附額の上位トップ5の自治体をみると、全国トップの宮崎県都城市が計848億円で、基金残高は2023年度末時点で586億円に達し、2018年度末から約55%増加しました。
次いで、2位の北海道紋別市は計804億円で、基金残高が270億円にまで拡大し、約4.8倍に膨らんでいます。
さらに、3位の北海道根室市、4位の白糠町、5位の大阪府泉佐野市と続きますが、上位トップ5の自治体の基金は5年間で計81%も増えました。いずれの自治体も人気の返礼品を数多くそろえ、PRにも力を入れています。
2 寄附金が多く入っても、国からの交付税は減らされない
ふるさと納税による寄附金収入は、自治体にとって臨時の収入として扱われ、税収とは扱われません。
通常、税収が多い自治体は国から交付される地方交付税が減額されますが、寄附金は税収とは扱われないので、寄附金がどんなに多く集まっても、国から交付される地方交付税は減らされないという仕組みになっています。
その結果、返礼品競争で勝ち、多くの寄附を集めた自治体はますます豊かになる一方、寄附を“流出”させた自治体――つまり納税者が実際に住んでいる自治体――では税収が減少し、財源格差が広がる構図が生まれています。
財務省は2023年に、ふるさと納税による寄附を税収と同等の一般財源として扱うことを検討すべきだと問題提起しました。制度の根本的な見直しを促す動きも出始めています。
3 「ふるさと納税」を見直す時期が来た?
自治体が1年で使い切れないほどの寄附を集め続けることができる現在の制度には、やはり課題があるといえます。
制度の公平性や持続可能性を確保するためにも、自治体が1年間に募集できる寄附金額の上限を設けるなど、新たなルールの検討が求められるでしょう。